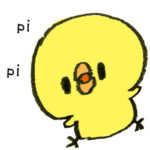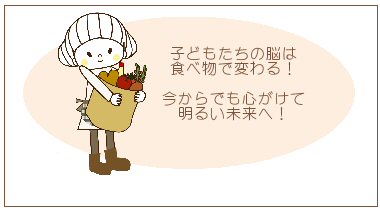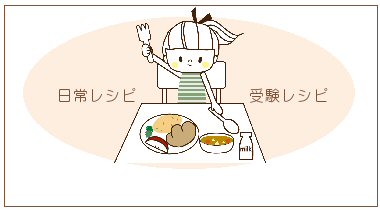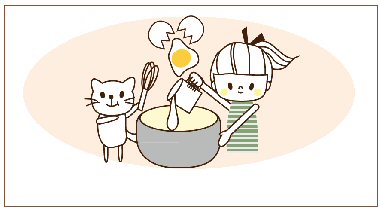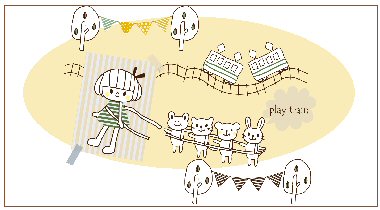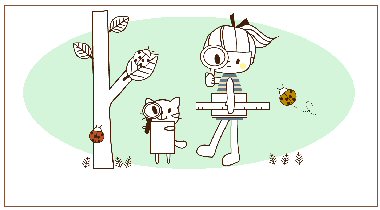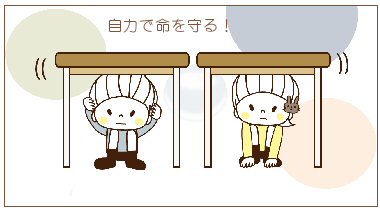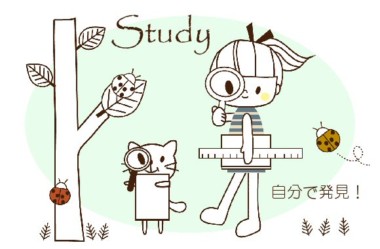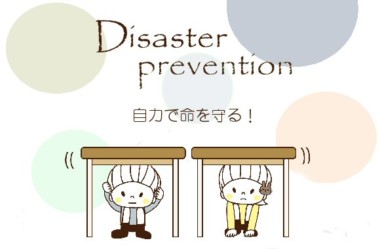何よりも健康で育ってほしい…
子供には命の大切さを伝えていきたい…
その願いは、どの親も同じです。
Contents
子育ての4つの教訓!犯罪と食は関連している!命の教育とは…
社会に広めたい「子育て四訓」という話の中で、とても感銘を受けたので、残しておきます。
- 乳児はしっかり肌を離すな
- 幼児は肌を離せ、手を離すな
- 少年は手を離せ、目を離すな
- 青年は目を離せ、心を離すな
これは、山口県にする教育者の方が、長年の教育経験からまとめられた話です。
子供を育てあげ、孫がいる生活をしていますが、育児を振り返ってみると、ほんとうにそうだなぁ…と思うのです。
イギリスの精神科医のジョン・ボウルビィ博士の「愛着理論」というものがあります。
- 第1段階(生後12週頃まで)
赤ちゃんの本能的で反射的な行動が、育ててくれる人の養育行動を引き出す - 第2段階(生後6カ月頃まで)
育ててくれる何人かの特定の人(特に母親)に対して、微笑み声を出すようになる - 第3段階(2歳頃まで)
母親や育ててくれる人と他人をはっきり区別して、人見知りをしながらも、一定の距離の中で安心して行動し、冒険をするようになる - 第4段階(3歳から始まる)
身体的接触を必要としなくなり、母親が用事があって距離をおいても、「用事が済んだら必ず戻ってくる」と信じ、学習します。
この四段階を経てできる特別な信頼関係が「愛着」で、子供の成長や発達に大きく影響します。
スキンシップは、子供の成長と人間形成の上でとても大切です。
自分を大切にできる子に育てる命の教育

赤ちゃんが生まれて、かわいい…守ってあげたい…と、小さな我が子を見て、親は感慨深い思いになるのではないでしょうか。
しかし、親にとっての生活は、楽しくて幸せばかりを感じてはいられず、朝晩関係なく泣く赤ちゃんにイライラしたり、成長過程でちょっとでも他の子よりも遅れていることがあったら、その子の優れている部分を見てあげるよりも、自分の育児が間違っているのではないか?とイライラする。
思春期になった子供は、親の見栄や理想通りに育っていないことの言葉を、敏感にキャッチして反抗したり、心の中で不信感がうまれ、肝心なことを親に話さなくなったりします。
親を嫌うと、その人の子…という血縁関係から、自暴自棄になる場合もあります。
若しくは、思春期までに「命・自分を大切に愛する」ことを教えてあげられなかったら、暴力事件や売春やリストカット…と、自分と他人を傷つけることをしてしまう。
それを“悪”と考えてもいない。
そして、命のもう一つの価値観…お金の問題があります。
少女売春をする彼女達はお金が欲しいという理由で…
いじめのひとつでお金にたかることでお金を手に入れる子も…
命と同等に“お金”が扱われていきます。
それは社会の傾向から子供にはそう感じさせてしまう何かがあるのではないでしょうか。
親がどのように「命とお金」について伝えていけばいいのでしょう。
どうしたら、「命の教育」ができるのでしょう…。
その、はじめの一歩は“食”から始まります。
子供に対する「命の教育」

生まれたばかりの赤ちゃんは、生きていくために泣いてお腹が空いたことを訴えます。
そこから「命の連鎖…教育」が始まります。
長い人生の中、子供と食卓を共にするのは期間限定で、短期間なんです。
育児に奮闘中の方は、先が長く感じるかもしれませんが、どうですか?…
生まれたばかりと思っていたら、いつの間にか大きくなっていませんか?
小さな子供と毎日慌ただしくて、にぎやか(うるさい…かな?)な生活をしていると、この時間が永遠に続いて途方もない気持ちになりがちです。
必ず、子供は経済的にも精神的にも、親からはいつか自立していきます。
そんなことを想像すると、当たり前のように家族で囲む食卓は、数年間だけの奇跡の幸せな時間なんです。
いただきます!おいしい!…ごちそうさま!…と言い合うことは、食卓でいっしょに「明日の命と幸せ」が続くと、当たり前のことに感じますが、実はとてもありがたい感謝することなのです。
お金に愛情の代わりをさせない心構え
共働きが多い中、なかなかすべてごはんを手作りにすることは、難しいことだと思います。
食事はお金さえ払えば、用意することがでることから、手をぬきやすいのが食事の用意です。
惣菜や弁当になってしまうこともあるでしょう。
そのような状況でも、10歳の子には10歳の子の栄養と量が考えられ、3歳には3歳の子の栄養と量があります。
パックをあけてそのまま食べるのではなく、残さない量をバランスを考えてサラダなどを追加し、その理由も子供に伝えていくことで、ただ単にエサではなく、親が考えた“ごはん”にすることが大切です。
お金を渡して、何か食べておいて…というように、お金を愛情の代わりにしないようにすることが、とても大切です。
凶悪少年犯罪「食と犯罪の因果関係」警察調査

非行少年が嫌いな食事は「家庭料理」が多く、食卓を囲んでいなかったことが明らかになっています。
「少年犯罪と食」の関係については、以前から警察でも大きな関心を抱いている。98年に茨城県警、02年に群馬県警から少年犯罪と食についての調査報告が発表されている。県内で検挙・補導された中学生・高校生とほぼ同数の一般の中高生との食生活を比較したものであるが、両県警の調査結果はほぼ同じとなっている。「朝食を一人で食べる」「家以外で朝食を食べる」「夕食を一人で食べる」「家族で鍋を囲むことがない」というのが、非行少年、特に粗暴犯の大きな特徴である。また、間食では非行少年のほうがジュース類を一般少年らより多く飲んでいる。食事の好き嫌いをみると、非行少年は果物、牛乳、おひたし、ごまあえ、ご飯、野菜、味噌汁、魚の煮物が嫌いな子が多い。朝からカップ麺を食べるという子も非行少年には何人かいた。
茨城県警察本部少年課では「食事を親に作ってもらい、それを食するという習慣の乏しさは、非行と関係することがうかがえる」と、考察している。
多くの青少年犯罪の子供たちは、食事を共に過ごす人がいないのです。
複雑な家庭環境のため、家にいてもごはんが食べられない子や、親がごはんを作らない子供たちがいます。
しかし、母親(父親)が先に旅立ってしまった父子(母子)家庭で、料理は立派ではなかったけれど、一生懸命頑張っていっしょに過ごそうとしている親の愛情は伝わることから、お金で解決する“食事の手抜き”が問題を引き起こしてしまうのです。
ジャンクフードやファーストフードに依存した少年らの食生活が、少年凶悪犯罪を生み出している大きな要因とされています。
現在、親のどうしようもない事情によって、食事を食べられない子供たちのために、食堂を運営されている方がいらっしゃいます。
子供達は、空腹な上、帰るところがなく、心の故郷がないために人の愛に飢えているという状況であっても、温かい手料理・安心できる食卓が子供達の心を育てると思うのです。
温かい食卓が子供達の心を安定させ、心の土台を形成するのです。
子供時代の食習慣が一生の食習慣を決める

東京医科歯科大学東京医科歯科大学の上野正之准教授が、小学1年生から中学3年生までの子供を対象に、甘み・苦み・酸味・塩味と基本の4つの味覚を認識できるかどうかと調査をしました。
正しく認識できなかった子供は全体の31%に上がるという実態が明らかになりました。
人間には、舌の表面に味蕾という、味を感知する細胞があり、そこで感じた味を脳の味覚野に伝えています。
しかし、現代の子供が食べているインスタント食品や加工品などには、化学調味料がたくさんあった食べ物で、甘みが強い濃い味のする食べ物なので、子供の味覚がそれに慣れてしまって判断できなくなっているようです。
子供時代の食の習慣は、一生の食習慣になってしまうので、素材の味が感じられるように食事をつくる必要があるのです。
そして、食卓を囲むことは楽しくて、食べることは生きていくために必要なこと…感謝していただくということから、食卓で夫婦喧嘩や子供を批判するような会話は避けるようにしたいですね。
英国イースト・アングリア大学とケンブリッジ大学の研究で、17歳から19歳の少年少女の脳をスキャンして、彼らの親たちに子供が生まれてから11歳までの味わった嫌な経験や試練を思い出してもらい、脳の発達の関連を調べました。
- 親が子供の前で口論・喧嘩をする
- 両親の仲が悪い
- 親に傷つくようなことを言われた
- コミュニケーションがない
- 愛情が欠けている …など
…というようなことですが、上記のような家庭では「小脳が小さい」とのことでした。
小脳の働きは運動の制御・技能の学習・ストレスの制御などと言われていて、脳の発達に大きな影響を与えてしまうのです。
そして、食卓で親の喧嘩やお小言が多かったら、生きていくための食事が楽しくないモノへとなってしまいます。
親は、子供にいつも見られているのです。
命の教育は、子供に接する親の日常や、食の考え方から学んでいくのだと思います。
こどもの命の教育は、一番大切なことです。