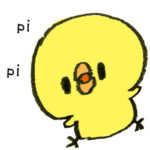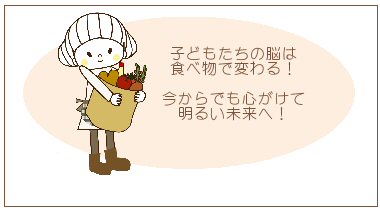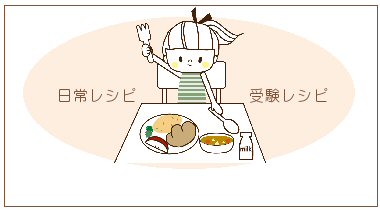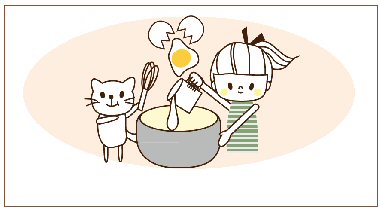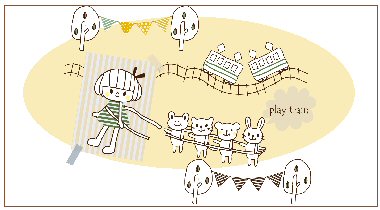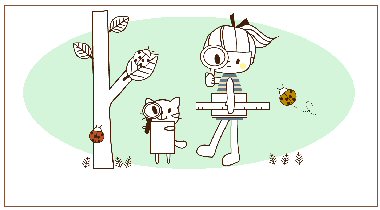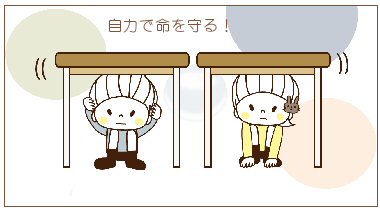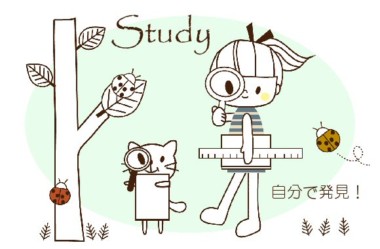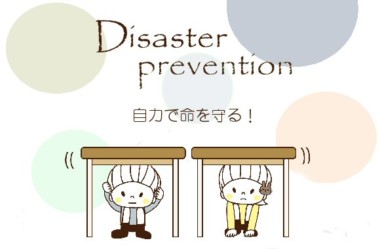Contents
子どもが自分で食を選び料理をする生き抜く力!想像力を育て実践調理
食べることに関して、男女問わずほとんどの子どもは興味を持っているのではないでしょうか。
大人が料理しているのをジーっと見ていて、子どもが料理に興味がある態度をとると、時間によって親はとても面倒くさく感じ、テレビやゲームをさせて興味を殺いでいかせんか?
子どもが興味を持った時が、想像力を伸ばすチャンス

子どもが料理に興味を持ち始めたら、一緒にクッキングを楽しむことが理想ですが、ゆっくりといっしょに料理ができない場合もあります。
私は、孫達に「折り紙でつくってみて!そして今度その通りに作ってみよう!」と、想像力を維持させたまま、楽しい雰囲気で次のステップに行くようにして、その場はゆるく遠ざけています。
急いでいる時は、どうしてもいっしょに料理ができない場合がありますよね。
しかし、約束は約束!
次の料理の時、若しくは次の日曜日など設定した日は、孫がイメージした料理を必ずいっしょに作るようにしています。
2歳ぐらいの時、粘土遊びの延長でパンなどをつくりはじめ、3歳のお誕生日のプレゼントで、子ども用の包丁やまな板などの調理器具をプレゼントしています。
8歳の孫は、自分の好きなハンバーグやシチュー、魚のホイル焼きなど、俗にいう花嫁修業的な料理は一通りできるようになっています。
味噌汁のダシも、冷蔵庫でつくる水ダシを作ったり、炊飯器にお米をセットするのも孫の役目にしています。
「お手伝いする〜」など、子どもから言うようになったら、チャンスです。
いっしょに調理をはじめて「違う!」「遅い!」「それじゃダメ!」「もぉ~ちゃんとして!」といった言葉は禁句です。
子どもと料理をすると、どうしても思うように進まなかったりこぼしたりして、大人がイライラしてしてつい怒鳴ってしまうことがあるのではないでしょうか。
大人にとっては簡単にできることでも、子どもにとっては未知の世界です。
ネガティブな表現はできるだけ避け、こぼしても「大丈夫!」形がこわれても「すごいね~ここまでできるんだ♪もうっちょっとこうすると、もっとすごいよ!」など、ポジティブな言葉をかけるように意識しましょう。
子どもにとって、親や大人に褒められたり、喜んでもらえることは、愛を感じる絶対的な安心感で、次のステップにいきたいという前向きな気持ちになります。
そして、お子さんと料理をする際は、四季の移り変わりによって旬のモノがあることは地球に変化や世界や日本の地域的特徴を知るようになりますし、料理中に起こる食材の変化は科学に結びつきます。
そして、目の前にある食材は、どんな気持ちで生産する人達は育て、私たちの食卓まで届けてくれているのか…と、いろいろと話しながら想像するようにしたいですね。
孫は、90歳のひいじいちゃんには、やわらかくするために時間を長めに煮たり、素材を細かく切ったりして、年齢による配慮もするようになりました。
「おおじぃちゃん、喜ぶかな?」…という質問に、笑顔で「〇〇ちゃんはやさしいね♪きっと大喜びするよ~」と私は答えますが、そうやって人に対する配慮も考えられるようになるのだと思うのです。
料理ひとつでも、様々な角度から想像力を育てることができます。
想像力を育てる実践調理は、具体的にイメージする力がつく

料理をしたいと言った孫に、イメージをしたものを折り紙でつくって、必要な材料を書いてもらっています。
イメージしたものをつくるための準備を想像し、次は段取りをシュミレーションしてもらっています。
「想像力」とは、ブリタニカ国際大百科事典では、「表象能力のこと。過去の像を再生する再生的想像力と,新しい像を生み出す創造的想像力に区別」と書かれていました。
自分が経験した過去のことと、経験したことがないけれども、こうなったらいいな…と、思う両方を具体的に思い描くことです。
想像力が欠如していると、問題に直面したときに解決策が少なくなってしまうことや、対人関係でも問題解決能力がなく、余計なトラブルを抱えてしまうことがあります。
その危険なイメージ認識の欠落が事故に繋がる場合さえあります。
想像力のある人は、さまざまな可能性を思いつくことができるので、危険管理や問題解決、他の人の感情に共感する能力なども高まると言われています。
日本教材文化研究財団の引用です。
先に挙げた傾向を持つ人(引用者注:思いつく解決策が少なく、人間関係のトラブルが悪化しがちな子供のこと)は、特に解決方法にバリエーションがない。それはその過程に於ける”様々な可能性”を”想像する力”が足りなかったからではないだろうか。そのために窮屈で不安定な時間を過ごしているように見えた。そのような事態に遭わないためには豊かな想像力を身につけることが重要なのではないだろうか。
<引用元:”想像力”を育てる関わり方>
想像力は、ただいろいろな遊びや将来に繋がることが思いつけて楽しい…と、いうだけのものではありません。
料理をするひとつでも、様々な角度から想像すると、危険を伴うことですが、安全確認をすることの重要性を感じることができますし、調理で熱を加えることで変わっていく様々な食材と、調味料を加えることで味が変わる…
そういう変化を楽しみながら、どうしてなのだろう?…と考えることが、人間が社会で生きていく中で「土台」となる能力が備わっていきます。
自分で食を選び料理をする生き抜く力

今回はハンバーグづくりからすべて、8歳の孫がひとりで作っています。
孫自身は失敗したと思った箇所があるようですが、頑張ったと思います。
家族が多く大人の私でも大変なのですが、今回は7人分のお弁当をずっと集中して作っていました。
本人曰く、栄養も考えてメニューを考えたと言っていますが、自分の好きなモノを作ったような気がします。
我家では赤いウインナーは添加物が多いので、普段は使わないのですが、今回はどうしても「タコちゃんウインナー」を作りたかったとか…。
味が4本になっちゃって8本に切れない…という部分が、失敗したと思ったところだそうです。
ただ、基本的な彩も考え、ハンバーグも小さな手でひき肉や玉ねぎをこねるのに苦労したようですが、おいしくできていました。
折り紙で作ったお弁当が、実際にひとりでできた孫は、すごくうれしそう…。
栄養を考えて食材を選ぶことも、多くの知識があれば健康を維持できることを、子どもなりに理解しています。
今回のお弁当は総合的に野菜が少なく、本当のところは「副菜」で野菜プラスした方がいいのですが、8歳の子どもが彩を中心に考える内容としてはよかったのかなぁ…と思っています。
苦労をしても、このような成功経験が、子どもにとってとても大切なことと思います。

生き方を見つけるための想像力
当ブログの他に、災害ブログがあるのですが、そこでは30年以内で大きな地震がくることを前提に様々な情報を提供しています。
私は60歳なので、その大災害を経験するのかどうかはわかりませんが、孫達は必ず経験をすることになります。
息子たちには、何があってもいいようにサバイバル的なことは経験させています。
孫達にも、生き延びる方法を何よりもイメージして欲しいと思うのです。
災害はいくら想像しても、現実は想像を超えていき、過去に例がないからと迷ってはいられません。
危険回避能力と生きていくための想像力が必要と考えています。
生きていくための能力は、想像力と知識が必要です。
汚れた水を備長炭などできれいにする方法や、雨水をいかに飲み水に近づけることができるか?
調理をしながら、きれいな水が蛇口をひねれば出てくることに感謝をしながらも、様々な話を子供たちは目を輝かして聞きます。
災害時、電気が通らないとき、IT企業に勤めていたり電気系統の遊びが大好きな若者たちは、電気を起こす方法が全くわからず、農家のおじいちゃんが近所の自家発電用の混合油や、各農家にある小さな太陽光発電を集めて避難所に光を与えた話があります。
おじぃちゃんは、そんなに物事を考えたのははじめてだぁ~と笑っていたそうですが、それは避難所にとって大きな光となります。
知識は多く持っていて邪魔になるものではありません。
想像力を働かせることによって、イメージ以上のことができることもあります。
子どもの知識を増やすのに、料理に限らず多くのチャンスがいっぱいあります。
子供の想像力を育む遊びを、一緒に楽しむ人と話をしながら膨らませることが何よりも子どもの脳を刺激していくのではないでしょうか。
子供が今どんなことを考えているのかな?
何をおもしろいと感じ、何をしたいと思っているのかな?…と、大人が子供の目線に立って想像してみましょう。
一緒に遊ぶことが、子供の想像力を育む第一歩です。
そして、料理は食材の話から“命”の話ができます。
命をいただくことの感謝、食べ物を食べられる感謝を教える大切な時間になります。
自分を大切に考えるのは、生きていくためにも“食”は重要ですし、人に思いやりの気持ちを自然に持てるようになるにも、親子で共に育む(TOMOIKU)ことだと考えます。
こどもの命の教育は、一番大切なことです。